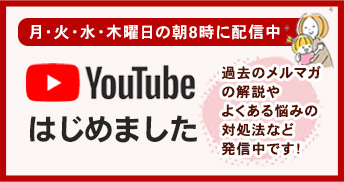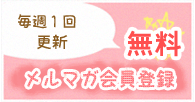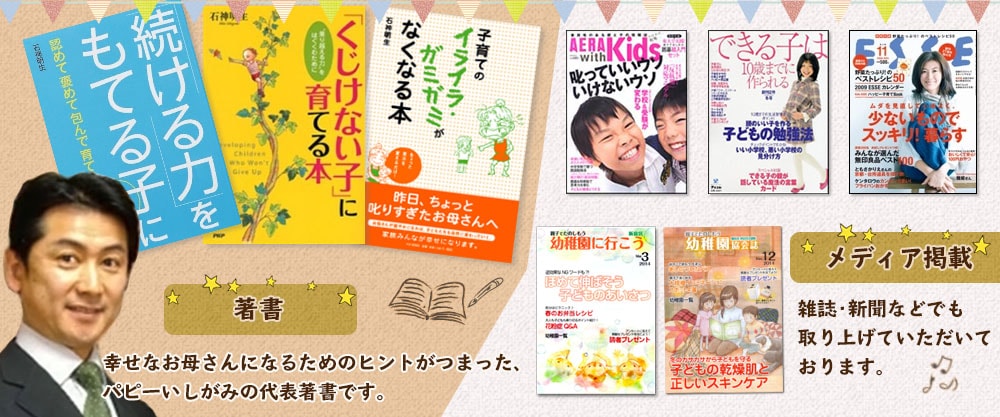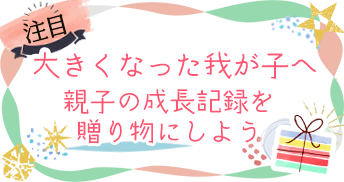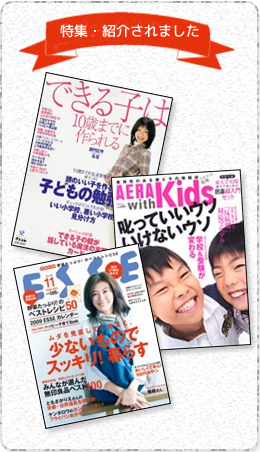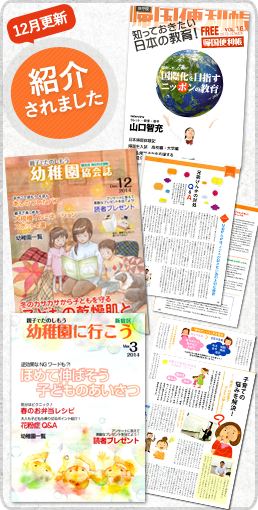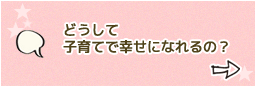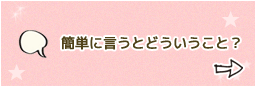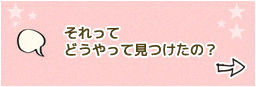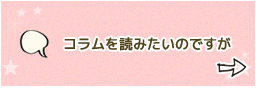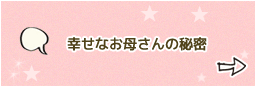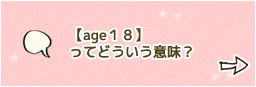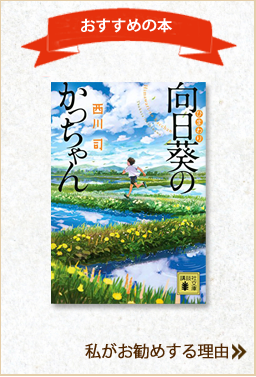第1353号 北海道講演会
パピーいしがみです。
(この文面を書いている今、9月20日 北海道 新千歳空港です)
昨日の北海道講演会と、北海道チームとの懇親会の興奮冷めやらぬ中、出発前のロビーで書いています。
今回の講演会は中学校のPTAが主催したもので、「その中学校PTAの関係者以外は参加できません!」だったので、どのような話をしたのか、その詳細をお伝えできれば・・・と思います。
講演会内容
お話を聞いてくださった方は約30名。さすがにPTA主催の会に参加される方々なので、真面目に熱心に聞いて下さいました。
先に「給食の試食」があったので、お腹がいっぱいになった後、そこで「じっと話を聞かなければならない」という眠たくなる(過酷な・笑)状況でも、
一人もうとうとすることなく、みなさん真剣に聞いてくださり、メモをとってくださる方も多く「隣・前後で考えてみましょう」の時にも、活発に話し合って下さいました。
まず、お伺いした中学校というのは、学校指定のTシャツと、ジャージを着て授業を受けるスタイルなんですがこの夏、暑かったですよね。
北海道の夏は短く「少し我慢すれば涼しくなる」のが常で、家庭でのエアコン装着率は、50%ぐらいだったそうです。
もちろん学校にはエアコンはついていません。
でも今年の「35度を超える気温」が続くの中でも、子供たちは長袖・長ズボンのジャージを脱ぎません(Tシャツ・短パンはもちろん推奨されています)。
そこには子供達なりの「考え方」があり、特にこの時期の中学生は、「みんなと違う」ことを嫌がります。
当然、体調の悪くなる子もいます。保健室に行く子も多かったと聞いています。
先生も、親も「まずはジャージを脱ぎなさい!」「Tシャツ・短パンなら涼しいでしょ!」と、いくら指導しても言うことを聞かない。
それについて本当に頭を痛めている・・・ということを聞いていました。
私の自己紹介をおえて、まずお話ししたのは「なぜ子供たちは上着の脱がないのか?」です。
まずは単刀直入にお聞きしました。
「子供たちはなぜ、脱がないと思いますか?」
そのお返事は「みんなと違うことをしたくないから」や「体毛が恥ずかしいからでは?」というお返事でした。
そして、私はこう言ったのです。
きっとみなさんは「どうしたもんか?」と悩んでいると思いますが、私はその話を聞いて、「子供たちは正しい環境で、正しく発達しているんだな」と思ったんです・・・と。
アイデンティティ
そしてそのお子さんたちが持ち始めている「自分らしさ」「私はこうしたい」という気持ち。そして親や先生に言われても、それを止めようとしない気持ち。
それは「アイデンティティ」が育ち始めている証拠です・・・と。
この時期のお子さんたちは、「自分らしさ」を考え始める時期。その『自分らしさ』のことを「アイデンティティ」というんですね。
発達心理学の権威、エリクエリクソンは、アイデンティティについてこう説明しています。
・・・アイデンティティとは、「人が成長の中で“自分とは何者か”を見つけていく過程。特に思春期には「自分探し」のような葛藤(アイデンティティの確立 vs 混乱)が起きやすく、大人になる中で少しずつ「自分らしさ」が固まっていく」・・・
でもその始まったばかりの「アイデンティティ」は、経験豊富な親から見ると、とてもとても幼稚。
「みんなと違ったことをしたくない」とか「体調不良になっても脱がない」「親からの話も聞かない」「ただ反発する」という程度でもあり、
経験豊富な親からすると「脱げばいいだけじゃん」と思うのですが、アイデンティティを守ること自体が子供の「アイデンティティ」でもあるので、
そこを踏みにじったり、強制して「力づくで従わせる」ということはしてはならないのですね。(健全な発育が阻害されるのです)
「じゃあ、どうすればいいのか?」というと、子供が「失敗する」ことを予想しながらも「子供の考えで」やらせてみる。
そして「失敗」をした時に、親がフォローできるような「準備をしておく」ことなんです。
今回の「ジャージを脱がない」ということについては、まずは「ジャージを脱がないでいると、暑くてたまらない」という「失敗」を経験させながら、フォローできることを探していく・・・ということになるのですが、
たとえば、今、ネクタイをしているサラリーマンなどがよく使う、「シャツシュット」という商品があります。(3段階の強さがあります)
これは、アルコールとメントールが含まれたスプレーで、Yシャツの下の肌着にスプレーしておくと、胸元をパタパタやるだけで、かなり涼しくなる・・・という優れものです。
サラリーマンだけでなく、室内競技のアスリート、炎天下、夏の盛りにゴルフをしたい方にも重宝されています。
ボトルの大きさが気になるのなら、小さな可愛い容器に入れ替えて持ち運んでもいい。
また、冷凍した保冷剤を保冷バックに入れて学校に持って行き、ハンカチに包んで首や脇に当てたりすることもいいですね。
携帯扇風機は認められているので、それで空気を送り込めば冷気が充満してかなり涼しく過ごせます。
反抗期の子への対処
でもこれは一例で・・・これが(思春期が始まった)「中学生」のお子さんがいらっしゃる方におすすめの接し方で、
子供達がこの「思春期」になってきた時、正しく成長しているお子さんは、以前の「言えば従う」ようなお子さんではなく、
「自分の考え」を持ち始めているから、親の言葉には耳をかさないし、どんなに強制・命令をしても動こうとはしません。
ですから親が「こうしなさい」ではなく「失敗する」と分かっていても、子供の「自分の思う通り」にやらせてみる。
(でも、失敗した時に、それをフォローする方法を準備しておいて)
「失敗しちゃったよ。どうしよう?」となった時に「こんな方法もあるよ」とそっとフォローすることで「あ、そうなんだ!やってみよう」となることが多いのですね。
失敗すれば、だれだって辛い思いをするので、その時に自分が考え付かなかった「いい方法」があれば、「あ、それもいいよね」と『自分で選んで』使う可能性もあるのです。
(それは強制も命令もせずに、結果的に親が望んだ通りになるということなんです)
そう。同じ結果を得るためにも、以前は直接「注意する」「行動させる」だったのですが、思春期になって「アイデンティティ」を考え始めた子供たちには、違う接し方が必要になるんですね。
親は『子供の成長』に従って「子供への接し方を変えていく」必要がある、ということなんです。
子育ての時期
ここまで話をして、次に「子育てっていつまでなの?」ってみなさん、どうお考えですか?と質問しました。
ホワイトボードに、3歳、6歳、12歳、15歳、18歳、20歳、22歳・・・と子供の成長と、年齢を図に書きました。
そして「みなさんが考える『子育て』とはいつまでか?」手を挙げていただきました。
幼稚園までだと思う人。小学校卒業までだと思う人、中学生卒業まで?高校まで?
大学まで?その先就職まで?
「いつ」が正しい、という決まりはないのですが、あなたは「どう考えるか?」と聞いたのですね。
そして多くの方は、15歳まで、18歳まで20・22歳まで、自立まで・・・というお答えでした。
そして私はこう言いました。
「ということは、みなさん、子育てには終わりがあって、その終わりは「自分で生活」をして「自立すること」だとお考えですよね」と。
みなさん、大きくうなづかれました。
そして次の課題です。
「ではみなさん、『子育て』って何だと思いますか?『子育ての概念』です」
「多分、お考えになったことはないと思うので、ここで隣の方や前後の方と話し合ってみてください・・・」とお願いしました。
3分間のお時間を使っていただきましたが、3分では終わらないほど熱心に話し合って下さいました。
・・・お考えを聞かせていただいて・・・
こちらも「それぞれの考え」でいいことなので、正解があるわけではないのですが、私がどう考えているか?をお伝えしました。
私は、子育てとは『子どもが自立し、自分で生活できるまでの、親がすべき援助と教育の期間』と考えていましたし、いまでもそう考えています。
子育ては「子供が自分で生活する」「自分で生きていく」ことができるようになるまでの(お金の援助を含む)様々な援助や協力と、(親がそのための様々な方法を)教えていく期間・・・ということなんですね。
教える内容には「マナー」「常識」もあれば「性」や「お金」もあります。(勉強なんてほんの1部分です)
それでも、そこには「終わり」(自立)がなくてはならないし、子供が大人になって自分の力で生活をするようになってほしい・・・という最終目的があるんですね。
8050問題
でも、今、「自分で生活できていない」「自立できていない」「自立しようとも思っていない(もう大人になってしまった)子供」がたくさんいます。
それを世間では「8050問題」といいます。
これ、確実な数字が出ているわけではないのですが、様々な資料から推察すると40歳~60歳の子供(すでに大人)を親が養育している例(8050問題家庭)がどれだけいるか?
というと概算で60万世帯だと言われています。日本の総世帯数は5,000万世帯ですからその中の60万世帯ということは・・・約1.2%となります。
これだけでも大変な数字ではありますが、それは40歳~60歳の「(大人になってしまった)子供」を対象に計算した場合で、それ以前の15歳~40歳(8050予備軍)は43万世帯あるそうです。
ということは、実際には約100万世帯(全世帯の2%)が「自立できていない大人を年老いた親がいまだに養育している」という異常な現実があるのですね。
そしてみなさんにこうお聞きしました。
「きっとみなさんの頭の中にの『あの家がそうだな』と2・3件は思い浮かぶという状況ではないでしょうか?」
やはり大きくうなづく方が何人もおられました。
でも、ご自分のお子さんがそうなったら、もしくは自分がその親となったら・・・どうでしょう?
できればそういうことは避けたいですよね。
子供達には、自分で仕事をし、しっかり自立をしてほしいはずです。
子育ての終わり
もしそうお考えの方には「これ」をしてほしいのです。
「子育てには『終わりがあること』を告げる」
これ、親としては「当たり前」だと思っていることですが、子供たちは誰も知らないのです。
だって生まれてからずっと「食べさせてもらうこと」「家で寝起きができること」「
テレビが見れること」「ゲームができること」「スマホが使えること」全部「当たり前」で育ってきましたから。
そして、今までにだって一度も「親があなたを援助しているんだよ」とか「あなたへの援助には終わりがあるよ」なんて聞いたことはないのです。
だから「スマホの使い方で親子で口論となり、母親を刺殺する」という事件まで起きるんですね。(2023年1月、静岡県御前崎市)
そんな不幸な結末にならないように、今の、中学生の段階で、お母さんが考えている「子育て」には『終わり』があること。
「子育ての期間は援助するけど、期間が終わったら援助はなくなる」ってことを子供に伝えてほしいんです。
それを聞いた子はびっくりします。
というのは「親が援助してくている」という事実を初めて知るからです。
また、「それには終わりがある」「その終わりはわずか数年後に訪れる」と知ることで、「じゃあその後どうしたらいいの?」って、真剣に考えるようになるのです。
そう。初めて「自分ごと」として考えるようになるのです。
そして、それをすることで、「自分は親に育てられている」という事実を知るのです。
そこには「親がいて自分がいる」という秩序と、「今まで親がお金を出していてくれたんだ」という現実。
そして「もうすぐ自分でなんとかしなくちゃならない時が来る」と真剣に考えるべき未来に訪れる問題が浮かび上がるんですね。
でもそうすることで「何をして生活費を稼げばいいだろう?」「もし進学したい時はどうすればいいだろう?」「生活するためには何が必要になるだろう?」と、具体的な疑問が浮かび、考えるようになるのですね。
そう。それこそが「自分ごと」として考え始めた瞬間です。
子供にとってはショックではあります。青天の霹靂です。
ですが、これを伝えるだけで、子供は
「今までは全て、親が出してくれていたんだ」
「あと数年後には自分で生活していかねばならない」
「自分で生きていかなければならないんだ」
と、すぐ先の未来の姿を想像して「どうすればいいか?」を具体的に考えていくようになるんです。(言い方を変えれば「伝えなければ気づかない」ままなのです)
もし高卒で働くのだとしたら、中学1年生ならあと6年。中学3年生ならあと3年。もちろん専門学校や、大学に行きたい場合はどうするのか?ご家庭で決めていただければいいですが、
その「子育ての終わり」を決めて、伝える。
そして「自分ごと」として考えさせる。
ただそれだけで、子供たちは「自分の立ち位置」「今後のこと」を真剣に考え始めます。ひいてはそれが「進学」や「仕事」にも広がっていくんですね。
ぜひ、お子さんが中学生の今、それを伝えてあげて下さい。
・・・・・・ここまでが前半ですが、すでに予定より15分も過ぎていました。
後半はメインの「10年後、我が子が社会から選ばれる人になるために」ですが、これも非常に内容が濃いので、こちらは来週にお話しさせていただきます♪・・・・・・・
北海道チームとの懇親会
上記の中学校での講演を終えた後、18時からの(北海道チームとの)懇親会会場に向かいました。
お酒は一切出ない懇親会ですが「お久しぶり~」から始まって、いつも会っている友達のように、テンションMAX!
でもみなさん、今年2月にお会いしたばかりの方々です。(その後、個人的にお会いしている方もおられるとはいえ)もう「仲間!」という雰囲気を感じます)
その中で私が注目していたのが、最初に目があった時の表情・目の輝きでした。
というのもランチ会を開催した2月以降も「子供とうまくいかない(嫌われているように感じる)んです・・・」と相談のあった方。
「学校の先生から指摘が多すぎて・・・」ダメ出しが多すぎることで子供が不安定になってしまった「せっかく良くなっていたのに・・・」というお悩みを聞いていた方。
「新たな病気が見つかった上に、私自身のメンタルが落ちていて・・・」と悩んでおられた方。
今までは、HSC傾向が強くて、あまり言葉が出てこなかったけど・・・今、少しずつよくなって、周りからも「見違えるようだ!」と驚かれている方。
それぞれお一人お一人の表情は?目の輝きは?子供の様子は?と注目していたのでした。
それぞれの表情は?
でも結論から言っちゃうと、みんないい表情をしていました。もちろんお母さんの目には優しさと力強さがありました。
「ああ、大丈夫。いい感じじゃん!」ってすぐに思いました。
ちょっと細かくお話しすると「子供とうまくいかないんです。嫌われているように感じるんです・・・」と言われていた方は、息子さんがお母さんべったり(笑)で、
最初は緊張していたものの、よく喋るし、お母さんに体を預けて、リラックスできていました。
もう「お母さん大好き!」って見ていてわかるし、もちろん、おかあさんもニコニコ。
「大丈夫みたいね?」と言いましたら「はい。ありがとうございます♪」と。
初めてあった時のお母さんは、少し笑顔が少な目で、沈んでいるようにも見えたんですが、今回は全く違いました。
また、うまくいき始めたら自分から「動き出したい!」と思われたみたいで、なんとジムに入会したんだそうです。(ご自分でも驚いておられました)
で、息子さんもスイミングを始めたんだけど、怖いみたいで「続けて欲しいけど、続くかどうか?」って心配されていたので、
それって、スイミングとは別に「お母さんと一緒にプールで遊ぶ」ことをすると「水泳→怖いもの」から「水遊び楽しい→水泳はその延長」になるので、克服できますよ♪とお伝えしておきました。
あくまで「お母さんが教える」のではなく「お母さんと水を使って遊ぶ」のですね。(教えるのは先生の仕事)
そうすると「楽しい」が先に来るので、何回か遊んでいるうちに「みて、こんなこと習ったよ!」と披露してくれたりして、知らないうちに子供の意欲が変わり、克服できちゃうんです。
息子さんは今、5歳ですが、ポケモンが大好きで「ポケモンカード?」のようなものをたくさん持っていて、そこからカタカナを全部覚えちゃったそうです。
「好き」って本当にすごくて、「好き」なものはどんどん知ろうとするので、好きなものが載っている本や説明書など「ちょっと難しいかな」と思うようなものでも、どんどん吸収してしまうんですね。
鉄道も好きなようなので、電車の本や、新幹線の本もとてもおすすめです♪
そんな話をしたら、お母さん「じゃあ次は・・・」ってワクワク考えているように感じました。これからが楽しみです♪
学校のダメ出し
この方は、幼少期からお悩みもあったのですが、徐々に良くなってきて、お子さんは、今年小学校3年生になったのでした。
でも先生が変わり、(まだ「指摘すること」「注意すること」が教育だと思っている人のようで)新年度になってから、お子さんへのダメ出し、親への指摘がとても多かったんですね。
学校の先生から指摘やダメ出しが多すぎることで子供が不安定になってしまって「せっかく良くなっていたのに・・・」というご相談をいただいていたのですが、
私がお伝えしたことは「先生が将来責任をとってくれるわけではない。先生の言葉は無視して、家では今まで通り、子供の良さを伝え、認め・褒めてください!」でした。
ファーストコンタクトのお母さんの顔は晴れやかでした♪
私は「あ、なんかいい感じみたいですね♪」と言ったら「えっわかりますか?(驚)」と。
学校で指摘があっても、家庭では以前と同じようにいえ、それ以上に良い傾向が増えていて、それが今度は学校でも表れているようで、だんだん先生からの指摘が減ってきたのだそうです。
そしてそれが成績にも表れ・・・「なんとあの子が100点とって帰ってくるようになったんです」・・・と言われていたので、
「じゃあ、そういう時は驚いて『あんた!すごいじゃん!』って言ってあげて♪」とお願いしておきました。(もう実行されているそうです)
今回、大学生になった2人のお子さん(もちろん自分の意思で参加)、がきてくれていたのですが、
その子達がお母さん思いの本当にいい子なので「うちの子はスーパーマン(注)になれるのかな?」と心配なさっていたのですが・・・
・・・(注)かつて親を困らせたり子育てが大変な子でも、必ず将来、親を助けるスーパーマンになる!という私の講座の一文から、会員さんたちは、そう育った子を「スーパーマン」と呼んでいます・・・
帰る頃には「うちの子もスーパーマンに成長させて、また、ご報告させていただきます!」という言葉をいただきました。
お母さんもこの時間内に、メンバーさんとお話しして「力」をもらったみたいです♪(メンバーさんとは参加された方々の意味)
病気が発覚・やる気の減退
次にご自分に病気が見つかり、気持ちが沈んでしまい、子育ても片付けもできなくて辛いんです・・・とご相談をいただいたおかあさんには、
「1日3回。自分を褒める言葉を考えてノートに書いて下さい」とお伝えしておきました。
もちろん他にもご自分で努力されたり、メンバーさんから「私もその病気持ってるよ」と同じ仲間もいると知って気持ちが楽になられたようです。
でも、お顔を見たすぐに「あ。乗り越えたな」と感じました。そしてお話しをしていると、言葉の端々にエネルギーを感じるのです。
今回は上の娘さんを連れて(前回はお一人)の参加でしたが、この娘さんも物おじしない子で(お母さんの横で安心していました)「この方ももう大丈夫!」と感じました。
今は自虐的に「あの頃は~」なんて笑って話せるような感じです。
「1日3回。自分を褒めてノートに書く」って結構時間がかかります。その代わり余分なことを考える暇もないので、ハードですが効果があります。
でも、もう今の調子なら「1日1回」にしてもいいんじゃないかな?って思います。
(直接言い忘れたので、メルマガ上でごめんなさい)
変化の表れてきた子
そして実は以前のメルマガでもお話ししたことがあるのですが、HSC傾向のあるお子さんがみるみる変わってきて「今年の運動会では大活躍」「楽しそうな笑顔が見れた」と感動されていたお母さんです。
お母さんは、お会いした瞬間から、もうニッコニコ。
お子さんは、当日、遠足で疲れていたはずなのに「僕も行きたい!」と言ってくれて、「自分の意思で」参加してくれました。
久しぶりにお会いした私には緊張していたみたいですが、以前よりずっと言葉も増えていて・・・
特に写真を撮る時に、さまざまなポーズができるのですね。
「慣れている?」のかもしれませんが、こうやって「自分らしさを出せるってすごいね」とお母さんとアイコンタクト!
お母さんも「ねえ!!!」って感じでした(^^)
あ~。今回も長くなってしまった。
この文章の長さで、伝えたい気持ちが大きいことがわかっちゃうね。
かなり減らしたんだけど・・・。
来週は「講演会」の後編「10年後、我が子が社会から選ばれる人になるために」の内容をお伝えします。
最後にお知らせです♪
【お知らせ】
(1)なんとインスタグラム・・・みなさんのご協力で、今、フォロワー15,300人を超えました。今、プレゼント企画を実装中ですので、お楽しみにして下さいね♪
https://www.instagram.com/papy_ishigami/
1日100人ぐらいづつ増えています。(びっくり)
なので、今年中には20,000超えるかも?って淡い期待を抱いています!!
(2)ボイシーもご好評をいただいています。「私は聞き流し派」という方も増えていて、朝の支度や通勤途中に聞いてくださっているそうです♪
家事をしながら耳だけ使っていただければ、一石二鳥で時短になりますね♪
「ダウンロード→パピーと検索」でお聞きいただけます。下記URLからダウンロードできます。
iPhone(アイフォン)をお使いの方
https://apps.apple.com/jp/app/voicy/id1115551289
Android(アンドロイド)をお使いの方
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.voicy.app.player&hl=ja
(3)【2026年ランチ会】まだまだ参加OK♪です。
1月 沖縄県ランチ会
2月 静岡県ランチ会
3月 岡山県ランチ会
4月 長野県ランチ会
5月 富山県ランチ会
6月 茨城県ランチ会
参加希望のご連絡はパピーいしがみまで。
メール送信先:age18_jp@yahoo.co.jp
(4)藤川理論コミュニティ(会員さんなら参加できます)
こちらも大盛況。参加ご希望の方はパピーいしがみまで。
メール送信先:age18_jp@yahoo.co.jp
今週は以上で終わりです。また来週。お会いしましょうね♪
https://www.age18.jp/ichiran.html
よろしかったらSNSもご覧ください♪
【Instagram】
https://www.instagram.com/papy_ishigami/
【YouTubeチャンネル】
「パピーいしがみ」チャンネル
【X(旧Twitter)】
https://twitter.com/papy_ishigami
【LINE公式アカウント】
https://lin.ee/CnDdGcd
【TikTok】
https://www.tiktok.com/@papy.ishigami
 【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。
【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。