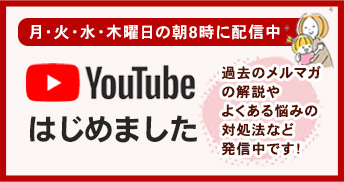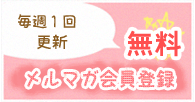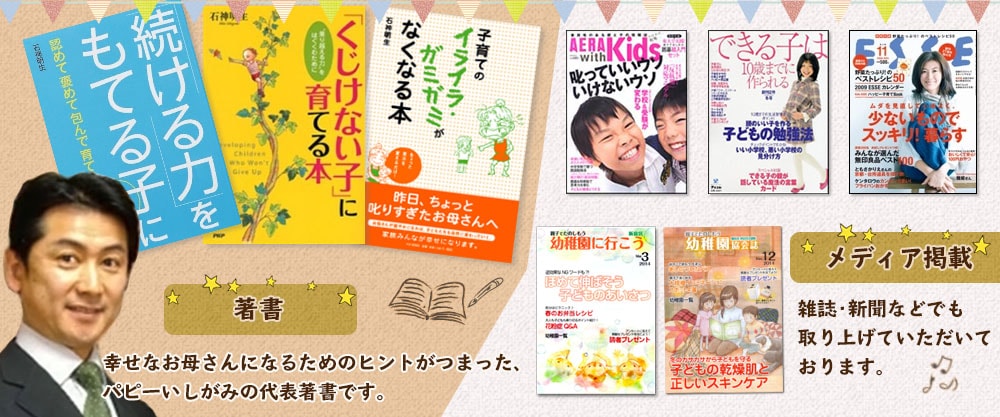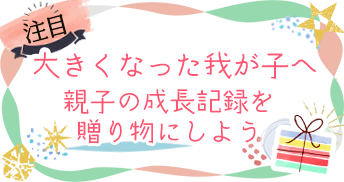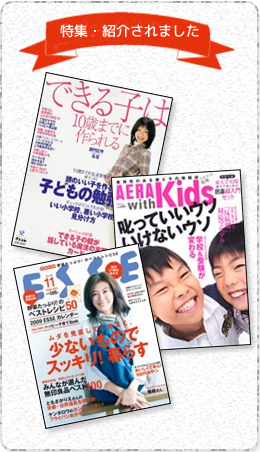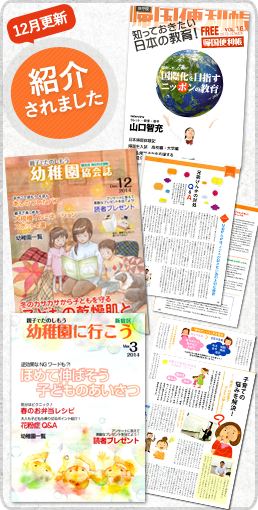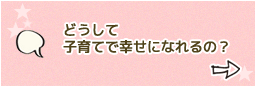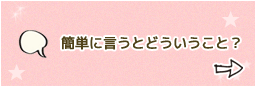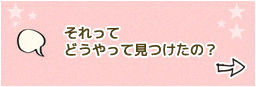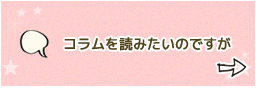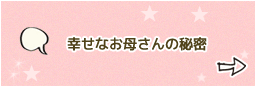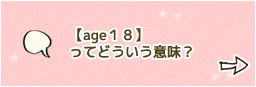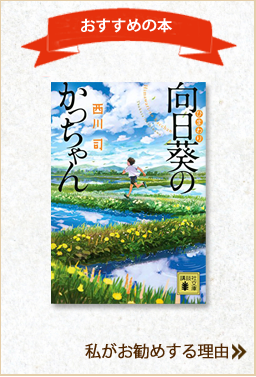第1359 号 認知能力と非認知能力
こんばんは。 パピーいしがみです。
11月に入りましたね。 今年もそろそろ終わりです。あと2ヶ月ですねー。
悔いなく今年を終えられそうですか?
「たった60日で何ができるの?」と思うかもしれないですが、いえいえ、まだ1年の6分の1はあるわけです。
今、何かやろうと思っても遅くないし、なんでも始めることはおすすめです。何か始めれば、2ヶ月もあれば何か結果が出ます。ぜひ貴重な時間を有効に使って、残りの2ヶ月をお過ごしくださいね。
さて、きょうは、最近よく耳にする「非認知能力」についてお話しします。
「認知能力」と「非認知能力」という言い方をよくしますが、今、この【非認知能力こそが大事だ!】と言う人がとても増えてきました。
こうやって「非認知能力」と聞くとすごく特別なものに感じませんか。
でもね。 このメルマガをご覧になっている方なら、その非認知能力については、すでに何度も何度もお話ししているんです。
でも今日は、それらを「非認知能力」という視点からお話しします。
認知能力と非認知能力
まずは、「認知能力」と「非認知能力」の違いについてお話しします。
では最初に「何が」認知能力なのか?なのですが、
簡単に言うと「頭の良さ」として測りやすい力です。
例えば、計算ができる、文字が読める・書ける、記憶する、論理的に考える、テストで点数が取れる・・・つまり、IQテストや学校のテストで測れる「知的な力」のことです。
反対に「非認知能力」とは、テストでは測れない「心の力・生きる力」のことです。
例えば、やり抜く力(すぐ諦めない、最後までがんばる)、
我慢する力(お菓子を後で食べる、順番を待てる)、
協調性(お友達と仲良く遊べる、譲り合える)、
好奇心(「なんで?」「やってみたい!」という気持ち)、
自己肯定感(「自分はできる」という自信)、
感情コントロール(怒ってもすぐ手が出ない)などです。
分かりやすく言うと・・・
認知能力 = 「できる力」(算数ができる、漢字が書ける)
非認知能力 = 「続ける力・乗り越える力」(難しくても諦めない、失敗しても立ち直る)
ということなんですね。
実は、将来の成功や幸せには「非認知能力がとても大切だ」と最近の研究でわかってきています。
勉強ができる?よりも、粘り強さや人と協力する力がある子が、社会で活躍しやすいんですね。
よく聞くじゃないですか?小中学校で「あんなにできないやつ」だったのに、事業で大成功して海外にまで支店を持っている・・・なんて。
だから私がよく言いますよね。「たがか勉強で・・・」とか「記憶力だけ良くたって・・・」とか、「 学校の成績だけが大事なんじゃない」って。
要は、子供たちは「大人」になるために育ち、「社会」に出て働いて、自分で生活し、 また自分の家庭を作ったりして、 自分で自分の人生を楽しみ、喜びを感じるのが今後の目的なんですから、
そこに行くまでの間に きちんと「社会で生活できる」「社会の一員となって生きていけるスキル」を身につけなければ意味がないということなんですね。
でも今までの教育って「認知能力」を 高めることばっかりでした。
そして最も必要な「非認知能力」の向上は「家庭でやってくださいね♪」というスタンスだったんです。(もちろん学校では教えられないのですが)
だから少々のつまずきで ドロップアウトしてしまう子がいっぱいいるし、 8050問題のように、自分の人生は切り開けない。 乗り越えられない、這い上がれない人が(社会問題になるほど)いっぱい出てしまうんですね。
私はこれは今までの日本の「教育制度」の問題だと思っています。
でも、相変わらず「勉強勉強」と言っている親御さんが本当に多いんです。
実際、日本で子育てをしている95%のご家庭はそうだと思います。
でも、このメルマガを読んでいらっしゃる方は、私が「 勉強よりも大事なものがある」と、しつこく言っているので、多分、まずは何が大事か?を理解してくださっていると思います。
そんな 私がもう20年前から言っている『勉強よりも大事なものがある』が、 やっとこの頃お気づきになる方が 現れてきたってことなんですね。
非認知能力には何がある?
この「非認知能力」を例えばジェミニくん(AI)で調べてみると、ずらずらといくつも出てきますが、私はそんなにたくさん知らなくても、4つ。もしくは8つ。多くても12個知っておけば十分だと思います。
では、大事なところからお話ししますね。
(1)絶対に身につけたい「非認知能力」
1、自己肯定感:「自分はできる、価値がある」と思える力
2、レジリエンス力:失敗や困難から立ち直る力
3、やり抜く力:最後まで諦めずにやり遂げる力
4、問題解決力:困ったときに自分で解決策を考える力
(2)できればあった方がいい「非認知能力」
5、主体性:自分から進んで行動する力
6、感情コントロール力:怒りや不安を上手に抑える力
7、コミュニケーション力:相手に伝え、聞く力
8、時間管理力 :時間を計画的に使う力
(3)ここまであれば十分な「非認知能力」
9、創造的思考力:新しいアイデアを生み出す力
10、批判的思考力:情報を見極め、考える力
11、メタ認知力:自分の考えを客観的に見る力
12、社会性・共感力:相手の気持ちを理解し協力する力
私がよくお話ししている内容は、(1)と(2)で網羅されている・・・と感じませんか?
そして、学校の勉強などの認知能力は(1)と(2)の間ぐらいの順番です。
特に、問題解決能力がなかったら、社会では必要な人だとは認識されないですよね。
やり抜く力がなかったら、結局仕事も中途半端で終わるってことになりますよね。
レジリエンス力がなかったら、小さなつまずきでドロップアウトして立ち上がれなくなってしまいます。
自己肯定感がなかったら、そもそも、社会に出たり、知らない人に会ったりすることが怖くて、自分一人では何もできないでしょう。
お分かりになりますよね。
だから「勉強なんて二の次です!」と声を大にして言っているし、「もっと大事なことがある」と言うのも、こういうことなんです。
焦って頑張る必要なし!
でも、だからといって注意してほしいのは、「非認知能力」をシャカリキになって、子供に付けさせようとする必要はない!と、いうことです。
例えば「問題解決能力」が無くても、「コミュニケーション力(伝え・聞く力)」があれば、先輩や友達から聞いたり教えてもらうことができますよね。
時間管理能力がなくても、スケジュールをスマホにインプットしておけば15分前にリマインド(教えてもらう)ことができます。
このように非認知能力は、何かの他の能力があれば補填できるし、テクノロジーを使って代替することもできるんです。
(でも認知能力は「イエスかノー」か、「知ってるか知らない」か、「0か1」か?それだけで、どんなに頑張っても人の知識はAIには太刀打ちできません。だから認知能力に価値がなくなっていくのです)
「非認知能力」もAIが発達してきて、(3)の創造的思考力・批判的思考力・メタ認知力・社会性・共感力を、AIに教えてもらうことができるようになっています。
例えば・・・
以前は、アイデアを出すことや、創造的に生み出すこと、作品を作り出すことは「クリエイティブ」とか「アーティスティック」と言われました。
でも今はこれらをAIに「○○のアイデアを教えて」とか、「こういう作品を作りたいんだけど、サンプル出して」と言えば、いくらでも出てきます。
企画立案などはもちろん、芸術の分野であっても、絵・写真・音楽・詩・小説・・・・際限がありません。
「メタ認知」に関しても、「私はこう思うけどどうかな?」と聞けば、客観的な考え方・見方を教えてくれます。
ですから、
1、自己肯定感:「自分はできる、価値がある」と思える力
2、レジリエンス力:失敗や困難から立ち直る力
3、やり抜く力:最後まで諦めずにやり遂げる力
4、問題解決力:困ったときに自分で解決策を考える力
これさえ持っていれば、十分世のを中渡っていけるし、成人して自分で生活をし、なおかつその中で喜びを見つけ、楽しい人生を送れるっていうことなんです。
そのために何をするか?
このお話をするのはもう釈迦に説法と言いますか・・・
このメルマガを読んでいる方には「しつこい!」と言われそうですが、メルマガを読み始めて日が浅い方や、初めて読む方は、わからないこともあると思うので書いておきますね。
1、自己肯定感を身につけるには・・・
その子の「生の肯定」をし、「姿勢・考え・行動」を認め、存在価値を認識してあげること。肯定の言葉3:否定の言葉2で、常に「肯定」が上回るように意識すること。
2、レジリエンス力を身につけるには・・・
様々な経験・体験を通じて、子供に失敗をさせること。親も失敗を見せること。「できないこと、落ち込むこと、落胆・挫折」をしてもいいと認めること。そして「包む」で乗り越える経験をさせること。
3、やり抜く力を身につけるには・・・
まずは子供の持っている「好き」や「興味」を肯定すること。その上でチャレンジができ結果まで出せたこと。それが、うまく行った・行かなかった関係なく、やり遂げた、その「姿勢・考え・行動・経過・結果」を賞賛すること。
4、問題解決力を身につけるには・・・
チャレンジやトライをしてみて、すぐにはできなくても、最初は親も一緒に考えて一緒に行動をする。「こうやったらできるかな?」と仮説検証を繰り返して「できた」を経験させること。(PDCA)
ね。私が言っていること。講座やメルマガで話していること。そのまんまでしょう?(^^)
それと一緒に(まあ落ちこぼれない程度に)学校の勉強(認知能力)をしてくださればいいかな?と思います。
でも「非認知能力」の4つがある子は、自分から勉強もするんです。
なぜなら「自分に価値がある」と知っていて「乗り越える力」があり、「やり抜く力」がある上に「問題解決能力」があるからです。
(設問に答えるのも問題解決と同じ回路を使うのです)
「非認知能力」なんて言われると、とんでもなく素晴らしいことのように聞こえますが、会員さんたちはすでに「毎日実践」していると思いますし、そんなに目新しい話でもないし、そんなに「難しいこと」でもないんですね。
ということで、今週はこの辺で・・・。
最後に、いつものお知らせをしておきますね。
来週は、神奈川ランチ会についてのご報告ができると思います♪
お楽しみに〜(^^)
お知らせ
(1)【2026年ランチ会】
1月 沖縄県ランチ会
2月 静岡県ランチ会
3月 岡山県ランチ会
4月 長野県ランチ会
5月 富山県ランチ会
6月 茨城県ランチ会
参加希望のご連絡はパピーいしがみまで。
(2)藤川理論(分子栄養学)コミュニティ
(会員さんなら誰でも参加できます)
参加ご希望の方はパピーいしがみまで。
メール送信先:age18_jp@yahoo.co.jp
では、また来週。お会いしましょう(^^)
https://www.age18.jp/ichiran.html
よろしかったらSNSもご覧ください♪
【Instagram】
https://www.instagram.com/papy_ishigami/
【YouTubeチャンネル】
「パピーいしがみ」チャンネル
【X(旧Twitter)】
https://twitter.com/papy_ishigami
【LINE公式アカウント】
https://lin.ee/CnDdGcd
【TikTok】
https://www.tiktok.com/@papy.ishigami
 【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。
【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。
- いじめ・友達との喧嘩, その他, やる気, 自信がない