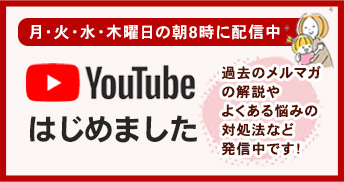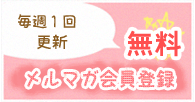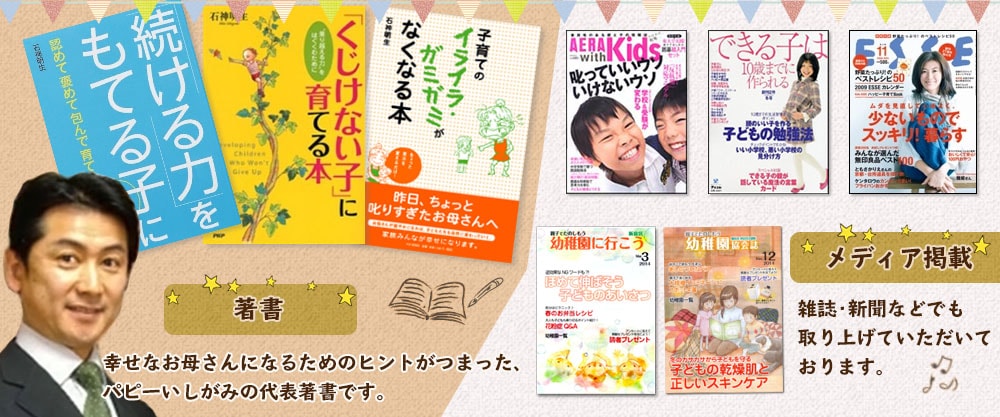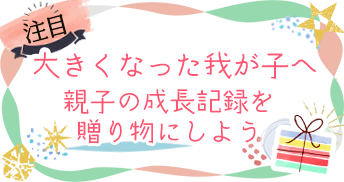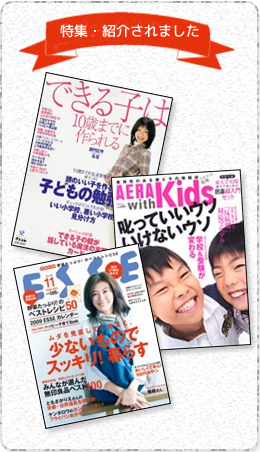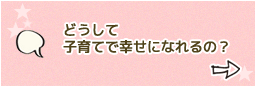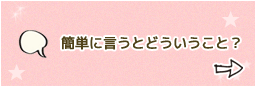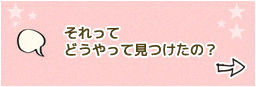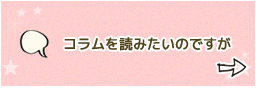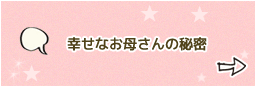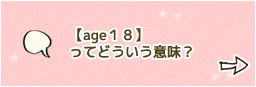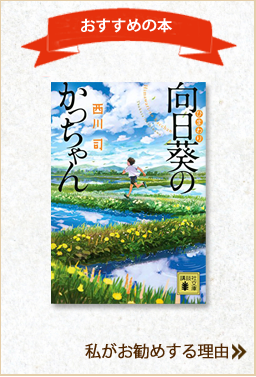第1357号 愛知県ランチ会(1)
こんばんは、パピーいしがみです。
本日、このメルマガをお送りしているのは、2025年10月19日(日)ですが、昨日と本日は愛知県名古屋市で、ランチ会を行いました。
今日は、10月18日に行われたランチ会の様子をご紹介できればと思います。
内容は・・・
1、一人っ子の場合、兄弟喧嘩ができないけど・・・
2、年少の男の子、指示が伝わりにくい・・・
3、小学校1年生の女の子、拗ねることが多い・・・
です。
まず、18日のランチ会には全部で8名の方、そしてお子さんもお一人参加されました。
ランチ会では皆さん最初はとても緊張されていますが、だんだん打ち解けて、帰る頃には昔から知り合いだったように親しくなってくださるのがとても嬉しいです。
お子さんは幼稚園の女の子で、私の名札を見て「パピー?パピーさん?」「パピーいしがみさんなのね」みたいな感じで、あまりにも可愛くて和やかな雰囲気から始まりました。
今回も、お一人10分ずつほどですが、お話をうかがい、ご回答もさせていただきました。
その中で「これは参考になるだろうな」と思う話がいくつかありましたので、ご紹介したいと思います。
一人っ子の場合、兄弟喧嘩ができないけど・・・
まず、お子さんが一人っ子の方って結構いらっしゃると思うのです。
でも私は「言いたいことが言えるようになる」ことがすごく大事で、「兄弟げんか」もさせてほしいとお願いしていますよね。
家庭内で一番近い兄弟でもけんかができないようでは、今後嫌なことがあったときに「言いたいことが言えなくなる」からです。
だから家庭で、しっかり自分の意見や言いたいことを言えるようになってほしいという意味で、「兄弟げんかはさせてくださいね」と言っています。
ただ、そもそも一人っ子の場合、その兄弟げんかはできないわけですよね。じゃあどうすればいいか?、という疑問もお持ちになっている方も多いと思います。
そのお母さんは、兄弟がいない分、私(母)とディスカッションができるようにしたい!とお考えになっていました。
それはとても正しいことで、やはりお母さんは子どもにとって一番近い存在なので、子どもが言いたいことがあるときに、ぜひお母さんとディスカッションしてほしいと思うんです。
(「ディスカッション」という言い方をしていますが、まあ。口喧嘩の意味です・笑)
ただ、時に子どもたちはきつい言い方、もしくは腹立たしい言い方もしますよね。
そんな時、どうしても頭に来てしまうことがあると思います。
そのお母さんも悩んでいたのですが「子どもたちが大きくなるにつれて、私たちの姿勢もだんだん変えていかなければならない、いつまでも子どもとバトルしているのがいいわけではない」というのも真実ですよね。
そのお母さんも、子どもから何か文句を言われたときも、できるだけ黙っておこうと努力もされていたそうです。
ですが、黙っておくと「自分の中で不満がどんどん積み重なってきて、思わず冷たく扱ってしまったり、イライラしてしまったりということが起きるのが辛いんです」という話でした。
これ、すごくよくわかります。
私はこの状況を「サンドバッグ」と呼んでいますが、サンドバッグにされ続けるとお母さんはストレスMAXになるんですね。
子どもに失敗させることもすごく大事だし、言いたいことを言えるためには、そこで子どもを言い負かす必要はない。
かといって、親のストレスもそのまま放ってはおけない。そんなときに、こんな言い方をしてみるといいですよとお伝えしました。
それは「あなた、その言い方おかしいんじゃないんですか」とだけ言ってみることです。
何も言わずに我慢していると強いストレスになりますし、後でムカムカしてきて、澱のようにたまってしまいます。
でも、子どもに対して「それは違うんじゃないですか?」と、わざと冷静で低いトーンでビシッと言うことで、子どもに対して一線を示すことができるんですね。
ただ我慢しているよりも、親としては「言うべきは言った」と納得もできますし、正直、少しスッキリもします。
その親の反応を見て子どもがどう考えるかは、あとは子どもの問題なので「是非、そんなふうに、ぜひやってみてください」とお伝えしました。
でも、そうやって子供が親に刃向かえるということは、とてもいいことで、それは子供が成長している証なんですね。
そのお子さんはもともと引っ込み思案、もしくは消極的な部分が強かったのですが、いいところノートを始めたことと、友達ができたことによって、少しずつ気持ちが前向きになってきているということでした。
その「少しの前向きさ」というのは、例えば「学級委員になりたかったけど・・・」といった変化です。
今まではそんな思いもなかったのですが「そう思ったけど・・・やっぱりやめた」という煮え切らない態度に、お母さんとしては「もう一歩頑張ってほしい」という気持ちもあったのですね。
でも、その「考え方が変わってきている」ということがとても大事で、考え方→行動→結果となる、最初の段階です。
ですから、私は「そういうふうに考えが変わってきたことだけでもすごいし、また友達と話すことで、どこまで話していいのか、どこまで言っていいのかが分かってくるので、とてもいい傾向。ぜひこのまま見守ってあげてください」とお伝えしておきました。
まだ友達とけんかする段階ではないですが、それでも少しずつ自分の意見が言えて、今までは消極的姿勢だったところから、少しだけでも積極性が見えてきたことは「とても喜ばしいこと」なんですね。
親だけでなく友達にも言いたいことが言えるようになってくると、もうこれは安心です。
「今はその過渡期ではありますが「今の形でいいですよ。楽しみに待っていてくださいね」とお伝えしておきました。
年少の男の子、指示が伝わりにくい・・・
そして次は「年少の男の子」のことです。その子は「やりたい!」と思ったら、何がなんでもやる。隠れてでもやる!という、私の小さい頃にそっくりなお子さんです。
お母さんとしては、発達の特性もあって親の指示が通りにくい、「泣きながら育てていた」という言葉が印象的でした。
そのお子さんもできることが増えてきたのですが、だんだん口が悪くなり「うるせー」とか「消えて」などの口走るようになり、「生死にかかわることは絶対に言ってはいけない!」と言っているけど、
それ以外も「あまり指示が通らない。どのように言ってあげたらいいのか?」というお悩みでした。
まず、このような場合は、ダメなことはやっぱりダメと言わなきゃいけません。
でも、それを言った後に、たまたまでもいいので、本人が自制したり、言葉を慎もうと思えたときには、「この頃は〇〇って言葉を言わなくなったよね。頑張ってるね」と、『できるようになったこと』を褒めてあげてほしいんですね。
親が「それはいけないよ」という否定の指示をしていると、子どもは聞く耳を持ちませんが、親が「昔はできなかったけど、今はできるようになったね」という肯定の表現をすると、
子どもは「え、僕のこと?もっと言って、もっと聞きたい」という姿勢になります。
今まで耳を塞いでいた状態から、耳を傾けて「もっと聞きたい」というモチベーションに変わるんです。
そして、「お母さんから褒められる状態をもう一度経験したい」と、モチベーションが湧いてくるので、それがその子の能力を高める最高のシチュエーションになるんですね。
また「先生から指摘を受けるのが辛い。今後、謝り続けなくてはいけないのか?と思うとしんどい」という気持ちも伺いました。
そうですよね。 その気持ちは本当によくわかります。でも、よくよく考えてくださいね。
幼稚園の先生や学校の先生は、その子の将来に責任を取ってくれるわけではありません。
現時点の先生の指摘はもっともかもしれませんが、先生は長くても2年で変わりますよね。つまり、その期間だけしか見ていないということなんです。
でも、私たちの子育ては20年も続きます。最後まで面倒を見て、責任を負うのは私たち親です。
だから「学校の先生の言葉を、真剣に聞く必要はありませんよ」とお伝えしました。
先生の言葉は現状を正しく捉えているかもしれませんが、親は将来を見て子育てをするんです。
「先生はそう思うかもしれないけれど、私は私のやり方でやります」との考えを持ち、先生の言葉には、儀礼的に「そうですか、申し訳ありません」と、陰で舌を出してさらっと流していいんです。
そして子供たちの変化は、注意したり、指摘したり、強制するよりも、自分で「〜〜したい!」と思う気持ちが最も効率よく飛躍的な変化を促します。
なぜならそれが『本人が変わりたい』と思うモチベーションになるからです。
そして私たちはそのモチベーションを持たせるために、 そんな小さな変化でもいいので、子どもたちにその変化を教えるんです。
「前は××だったけど今は○○になったね」とか、「前は難しかったけど今はできるようになったね」という感じです。
そして「あなたはこんなこともできる あんなこともできる」「あれもできるようになったし、これもできるようになった。すごいじゃん」 と、できるようになった事実を教えるんです。
すると指示が通りにくかった子ども「僕のいいところをもっと聞かせて!」と自分から耳をダンボにして聴くようになるんですね。
そう、指示が通りにくかったのではなく、否定の言葉は聞きたくなかったんです。
これらを肯定の言葉に変えることによって聞く力はぐんと高まるんですね。
そのお母さんは「今まで先生の言葉を真面目に聞きすぎていました」と言われ、 「そんなに真剣に聞かなくていい」と聞いて気持ちが楽になりました♪と言ってくださいました。
小学校1年生の女の子、拗ねることが多い・・・
こちらはご報告も含めて、ご相談もいただいたのですが、 そのご家庭には、中学1年生の娘さんと小学校1年生の娘さん、6歳差の2人の女の子がいらっしゃいます。
小1のお子さんは朝なかなか起きられなかったのですが、ある理由でパッと起きられるようになったそうです。
その理由は、今まで6年生だったお姉ちゃんが毎朝オムレツを作ってくれていたことにあります。
オムレツってなかなか技術が必要な料理ですが、それをお姉ちゃんが担当していたのです。
ところが、お姉ちゃんが中学に上がって忙しくなり、「お姉ちゃんの代わりにオムレツを作ってくれる?」と小1の娘さんに聞いたところ、
本人がとてもやる気になって、今は家族のオムレツを毎朝作っているそうです。お休みの日には、お父さんお母さんにコーヒーも入れてくれるのだそうです。
家族の中で自分の役割を持ち、みんなの笑顔を見る「喜び」を感じたことで、朝早く起きられるようになりまんだそうです。
今では、意気揚々と頑張ってくれているということでした。
お母さんとしては、そんな娘さんにもやっぱり少し心配があって、一つはお母さんの真似っ子、お姉ちゃんの真似っ子をすることです。
「主体性がないのでは?」という心配がありました。
ですが、やっぱり末っ子、もしくは年の離れたお子さんの場合、どうしてもお姉ちゃんがやっていることに憧れを持ちますし、兄弟姉妹の真似をしながら、どんどん自分の中に経験を積み重ねていくんですね。
なのでお母さんには「うちの娘もそうでした。うちの一番下の娘も、自分から『これをやりたい』と言い出したのは中学1年生でした」とお伝えしました。
もちろん本人がやりたいと思ったことは全面的に応援しましたし、それを親が修正したり導くことはありません。
「まだ小学校1年生でしたら、主体性がなくても大丈夫です。今は真似っ子をしながら、経験を積み重ねる時期ですから」とお伝えしておきました。
それと、もう一つのご不安が「すねることが多い」ということでした。
以前のメルマガで「すねんぼ(拗ねること)は損」とお伝えした回もありました。
お母さんはそのようにお子さんに言っておられたそうですが、もうその話をされているのですから、次の段階へ進んでいいんです。
「次の段階」というのは、子どもさんが少しでも拗ねる時間が短くなったら、「前は〇〇分拗ねていたけど、今は〇分になったね」というように、拗ねる時間が減ったことを肯定的に褒めてあげるんです。
そうすると、子どもは「自分の変化」と、拗ねる時間が減ったことを「お母さんが褒めてくれる」と知って、自分から拗ねる時間を短くしようとし始めるのです。
これは先ほどの年長の男の子の対処にちょっと似ていますよね。
指摘をするのではなく「少しでも起きたプラスの変化」を子どもに伝えて、子どもが自ら「そうなりたい」と思うようなシチュエーションを作っていくということなんですね。
私たちは、「指摘や指示で間違いを正す」と考えがちですが、強制や命令や忠告では、なかなか子どもは動かないんです。
でも、その子の変化、良くなったことを褒めるだけで、本人が自分から正そうとするんですね。
それはとんでもなく効果的な方法なので、ぜひ皆さんに試していただきたいと思います。
さて、まだまだお話したいことはあるのですが、 長くなりすぎちゃいますので今回は3件だけのご報告とさせていただきます。
最後に今回、ランチ会に参加してくださった方のグループラインで頂いた皆さんの感想をご紹介します。
ご感想
ひとりで出口のないトンネルの中にいるように感じていましたが、皆さんとお話しできて「自分ひとりではないな。皆さんも日々頑張っておられるんだな」と思い、私もまた頑張ろうと思いました。出会いに感謝します。
今日は「初めまして」の方ばかりでドキドキでしたが、皆さん笑顔がとても素敵で、話しやすい方ばかりでとても嬉しかったです。ありがとうございました。
本当に楽しく、あっという間の時間で、まだまだお話し足りませんでした。
身近に同じ志を持った仲間がいることや、相談できる安心感が心強いです。またぜひ集まりましょうね。今後ともよろしくお願いします。
今日は、パピーさんや皆さんと出会い、実際にたくさんお話しできて本当に感激でした。皆さん、どの「パピーメソッド」の話もすぐに「うんうん、あれね」となり、出会う前からチームだったような感覚を持てたことがとても嬉しかったです。
・・・・以上、愛知県ランチ会(1)のご報告でした。
【お知らせ】
(1)【2026年ランチ会】
1月 沖縄県ランチ会
2月 静岡県ランチ会
3月 岡山県ランチ会
4月 長野県ランチ会
5月 富山県ランチ会
6月 茨城県ランチ会
参加希望のご連絡はパピーいしがみまで。
(2)藤川理論(分子栄養学)コミュニティ
(会員さんなら誰でも参加できます)
参加ご希望の方はパピーいしがみまで。
メール送信先:age18_jp@yahoo.co.jp
次回は10月19日の愛知県ランチ会(2)のお話しをしたいと思います♪
では、また来週。お会いしましょう(^^)
https://www.age18.jp/ichiran.html
よろしかったらSNSもご覧ください♪
【Instagram】
https://www.instagram.com/papy_ishigami/
【YouTubeチャンネル】
「パピーいしがみ」チャンネル
【X(旧Twitter)】
https://twitter.com/papy_ishigami
【LINE公式アカウント】
https://lin.ee/CnDdGcd
【TikTok】
https://www.tiktok.com/@papy.ishigami
 【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。
【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。