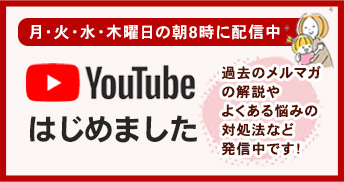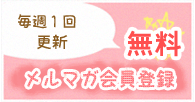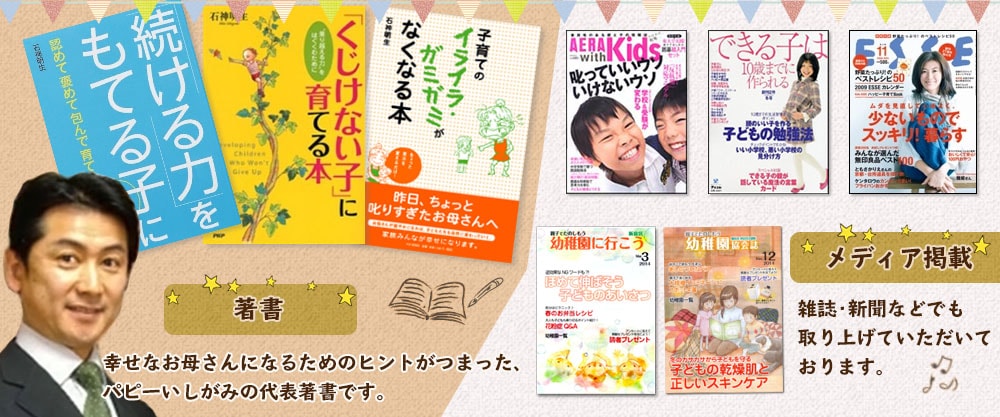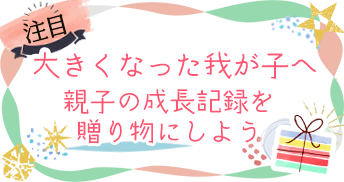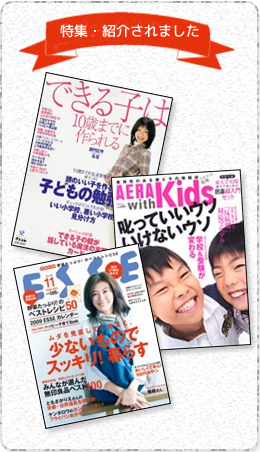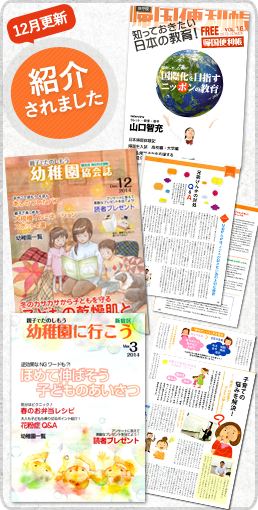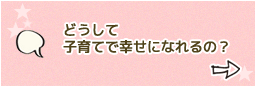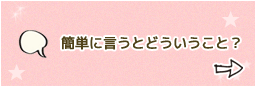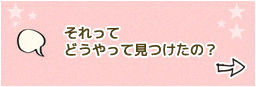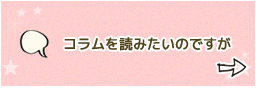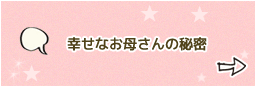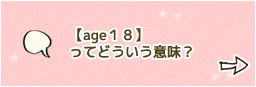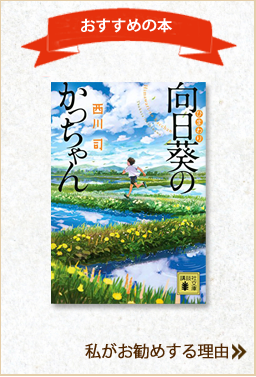第1347号 東京講演会
パピーいしがみです。
夏!ですね~。
静岡では8月6日、12時5分に気温が41.4度に達したそうです。
「そうです」と言うのは、私はその日、翌日の東京での講演会のために車で移動していたからです。
車内はエアコンで快適でしたが、東京の首都高の渋滞したトンネル内でも、外気温44度と表示されていました。
44度って・・・。と思いましたが、エンジンをかけた『動かない車』がいっぱいのトンネル内なら、ありえるかな~と思って窓を開けて手を出したら、確かに相当暖かかったです。
(エアコンのない車でここにいたら・・・もし車がオーバーヒートで止まったら・・・と思うとゾッとしました)
でもその日の静岡の最高気温は、歴代最高で、日本での最高気温に迫るものでした。ちなみに現在の日本最高気温は、今年の8月5日に記録された、群馬県伊勢崎市の41.8度。
今年は8月も早い段階で、最高気温が更新されているように、本当に危険な暑さですから、体調管理に気をつけてくださいね。
これから夏休みがはじまりますが、涼しい所か日陰でお過ごしくださいね。
さて今回は、先日8月7日に行われた東京都での講演会についてお話しします。
そうそう。前回のメルマガで「シークレット」とお伝えしたその場所ですが、板橋区にあります【板橋区弥生児童館】でした。
板橋区では一番新しい児童館らしくて、とても綺麗でいつも子供達、若いママさんたちで溢れているそうです。当日も元気な子供たちの声が響いていました(^^)。
職員さんたちも、明るくて、雰囲気が柔らかく、子供たちやママさんたちを笑顔で迎えておられました。
東京講演会・きっかけ
なぜ、今回、東京で講演会をすることになったのか?そのいきさつからお話ししたいのですが、その開催地となる児童館の館長さんが私のメルマガをずっと読んでくださっていて、もう18年になるそうです。
ご自分のお子さんは、すでに成人、自立をされたのですが、私が「講演会はしません」と言っている時から(相談者さんへのお返事の時間がなくなるのでずっと断っていました)
「いつになったら始まるのかな~?」とずっと待っていてくれたのだそうです。
ただ、その頃はまだ「館長さん」ではなかったので、権限はなかったのですが、5年前に館長さんになられて、
「これでいつでも呼ぶことができるぞ!」と準備万端、待ってくださっていたそうです。(それでも5年も待ってくださった・・・ことになります。申し訳ない・・・)
そして今年になって、私が「講演会しますので、呼んでください」とYouTubeやメルマガでお話ししたら、「待ってました♪」と一番にご連絡いただいたのが、その館長さんだったんですね。
そのいきさつがあったので、8月6日に、まずご挨拶・・・と寄った児童館では、すぐに打ち解け、昔からの知り合いのように1時間近く話し込んでしまいました。
(多分、職員さんたちは「本当に初対面?」と驚かれたと思います)
館長さんは、この道30年だそうで、それはそれは「子供たちのこと」「お母さんのこと」を真剣に考える温かい方でした。
そして今回は、0歳~1歳のお子さんがいらっしゃるママさんのための「第一部」。そして1歳以上で6歳ぐらいまでのママさんのための「第二部」と、二部制でお話しして欲しい!とご依頼をいただきました。
当日までにお申し込みくださっていた方がそれぞれ10人ぐらいだったのですが・・・「当日、きっと増えると思います」との言葉通り。
どちらも20人ほどの方が集まってくださいました。皆さん、それぞれお子さんを連れての参加でしたが、子供達もぐずることなく、皆さんとても真剣に耳を傾けてくださいました。
私としては、第一部で「認める」を。そして第二部で「褒める」と「包む」を。
また、両方ともに子育ての最終地点を考えて逆算すること。そして今、何をしたらいいか?と考えることや、
AIをスマホに入れて「こうやって使うといいよ」と実際のデモンストレーションを。
そして「お母さんが『お母さん自身』を褒めてください。言葉を口に出してください」とお願いしました。
例えば、
1、たった5分でいいからコーヒーをゆっくり飲む。or
2、ケーキなどを買ってきて時々自分にご褒美をあげる。and
3、「私ってよくやってる」「私って偉いじゃん」って言葉に出す・・・。
お母さんに余裕がないと、お子さんに対してもイライラしやすいことと。
私たちの脳は、「主語」をあまり認識しないので、もし自分が「よくやってる」「偉いじゃん」と言ったとしても、それを外からの情報だと、なんかホッとしたり、癒されること。
なので・・・ぜひ、試してみて♪とお伝えしておきました。
では、それぞれどんなお話をしたのか?メインの「認める」「褒める」についてご紹介します。
第一部:今だからこそ知っておきたい!赤ちゃんの『次のステップ』準備編
集まってくださった方が、皆さん、抱っこされている状態の赤ちゃん。もしくはまだお座り・・・ぐらいのお子さんでしたので、今、して欲しいことをお伝えしました。
それは「認める」「褒める」「包む」の最初の段階。「認める」です。
実はこの「認める」は、この3つの中でも、もっとも重要で、特にこの生後数ヶ月~1歳半、2歳までにはたっぷりしてあげて欲しいことなんですね。
それと「認める」で大事なことは「否定をしたり」「ジャッジをしたり」「正そうとして叱ったり」は『しない』ってこと。
では具体的にどんな接し方が必要か?と言えば「あなたがいてくれてうれしい」「あなたは大事な存在」「生まれてきてくれてありがとう」という気持ちで接するとことなんですね。
それは子供たちに「望まれて生まれてきた」「必要で大事な存在」と思ってもらうためです。
例えば、自分では気づかなくても、「赤ちゃんができた」と知った時は、誰もが喜んでくださったと思います。
(もしそうでなかったとしても、子供には「望まれて生まれた」と思ってもらいたいです)
そして生まれるまでの間、風邪を引かないように、転んだり、ショックを与えないように大事に過ごされ、「早く会いたいな~」とお考えになったと思います。
そしてとても辛い"出産"という長時間の試練を乗り越えた時も、大きな喜びがあったはず。
それらの「生まれてくれて嬉しかったこと」「待ち遠しかったこと」「出会えた時のよろこび」を忘れずに接してくださいね、ってことなんです。
そして「否定をしたり」「ジャッジをしたり」「正そうとして叱ったり」は『しない』のはなぜか?と言うと、
まだ善悪がわからない時期でもあるので、そこで「否定」や「叱る」をしても、それが「改善」に結びつくことはなく、
それをするとただただ「萎縮」や「行動しない子」になってしまうために、この時期は「褒めなくてもいいけど、指摘や否定、改善させようとはしない」ということに気をつけて欲しいんですね。
具体的にどうすればいいか?というと、例えば積み木を5つ積んでいたら「高く積んだね。5つも積めてすごいね」ではなく
「とっても真剣に積んでいたね」とか「そうっと崩れないように工夫していたね」とか、崩れても「バラバラってなっちゃったね。でもまた作り直すんだね」のように、
あくまで「実況中継」のアナウンサーのように、今、子供達がやっていることをよく見て、それを話してあげればいいんですね。
そしてもちろん「生まれてくれて嬉しかったこと」「待ち遠しかったこと」「出会えたと時のよろこび」があれば、その時のママのお顔は笑顔ですよね。
そんなふうに、子供たちが0の状態から「生の肯定」をしてもらって「自分は存在していいんだ」「望まれて生まれてきたんだ」という土台ができていると、
安心してそこに今後の経験が積み上がっていく・・・と言うことなんですね。
家を立てる時の基礎ができるんです。
でも、もちろん、それを「やってこなかった」からダメだ・・ではなく、これは気づいた時から始めてもらっていいんです。
・・・ここからは話していない内容ですが、このメルマガをお読みの方で、「え、私はやっていなかった」と思った方向けに書きますね。
赤ちゃんの場合は、具体的な方法としては上記ですが、例えば年齢が高い子だったら、その子がお腹にできたとわかった時の「喜び」の話しをしてあげる。
生まれてきた時のお母さん、お父さんのどんなふうに喜んだか?のエピソード。
また、おじいちゃん、おばあちゃんがどんなふうだったか?なども話してあげるといいですね。(それらが「生の肯定」「望まれて生まれてきた自分」を教えられます)
そして普段の関わりでも話を「聞く」姿勢。子供が話していても無視したり、適当に返事をするのではなく、
何か作業をしていたとしても「ふ~ん、そうなんだ」「へ~。それで」「それは笑っちゃうね」など、
「話を聞いてるよ」的な相槌を入れたり、リアクションを起こしたり・・・。「あなたの話をちゃんと聞いてますよ~」というアピールをしてほしいんですね。
そして子供が言いたいことを途中で遮ったり、話の腰を折ったり、親の意見を押し付けたり、頭ごなしに否定したり・・・はせずに、
まずは話を聞いて(話を聞くって「要望をなんでも叶えてあげる」という意味ではなく、文字通り「耳を傾ける」ってことです)子供が言いたいことを全部言わせてあげて欲しいんですね。
その「聞いてもらう」だけでも話す方は「聞いてもらえた」満足があるんです。
もし、その考え方を修正させたいのなら、全部聞いたそのあとで「違う」ことの説明をするようにすればいいんですね。
・・・とこれらが「認める」になります。
そして次の段階として「褒める」「包む」をお伝えしたのですが、「認める」から「褒める」に移行する時の目安として、「イヤイヤ期が始まる頃~」って考えていただくといいかな?と思います。
知恵がついてきて「いや」と言って自己主張をし出す。そうなると「褒める」をすることで「こうするとお母さんが喜んでくれるんだ」ってわかるようになるからです。
第二部:イヤイヤ期も怖くない!「次にくる成長」を知って楽しく乗り切る方法
・・・まず、これ、言い忘れちゃったと思っているのですが・・・
「イヤイヤ期」になると、多くの方が「イヤイヤ」をやめさせたい、素直に言うことを聞いて欲しい、とお考えになりますが、
子供が「本当にイヤでNO!を言っている」わけではなく、自分が「イヤ」と言った時の、ママの困った顔やリアクションを初めて見るので、そこに興味があって・・・や「言ってみたい」という気持ちの場合もあって、
子供の「イヤイヤ」をあまり重大に感じなくてもいいんですね。
そこで対策として「本人に選択させる」という方法があります。
例えば、お風呂に入りましょう・・・と言った時、「お風呂入りたくない」「イヤイヤ」となったとしたら、「入ろうよ~」「ね~、さっぱりしよう!」ではなく、
「お風呂で遊ぶおもちゃ、赤い船にする?それとも緑色のジョーロにする?」のように「お風呂に入る・入らない」をすっ飛ばして
(もう入る前提で)「どっちにする?」って質問するのですね。
すると、子供の意識は「入る・入らない」ではなく「どちらのおもちゃにするか?」に向かい、2択のどちらかを選択する、ということに集中するのです。
そして「赤い船にする」と言った時、それは誰かに決められたものではなく、自分で決めたことですよね。その「自分の選択」が子供本人の満足感を刺激するのです。
そして・・・「お風呂に入る」一択の中でどちらかのおもちゃを選び、ご機嫌よくお風呂に入ることができたりするわけです。
もちろん、これがうまくいかない場合もあるし、そんな時の対策もあるのですが、「イヤイヤ」は、そんなに大きな問題ではないんですね。
そして・・・「褒める」についてですが、この「褒める」を話す時、多くの方が「私も育児書を読んで実践しています」という方が多いのですが、
多くの方は「結果」だけを褒めることが多いです。
でもこの「結果」だけを褒めることには弊害もあって、一つは「結果が良くないと褒めてもらえない」と認識してしまうこと。
そうなると「できることは頑張るけど、難しいことや失敗しそうなことにチャレンジすることがなくなる」ことや、
「結果さえ良ければ、いいんだ」(そのためには何をしても・・・)というふうに考えてしまうようになる、ってことなんですね。
「褒める」その機会ですが、全部で5つある、と私は思っています。
それは「考え方」「行動」「継続」「努力」「結果」です。
でも多くの方の褒めるは「結果」についてがとても多くて、例えば「◯◯できたね。すごいね」とか「◯◯したんだね、偉いね」のようにです。
でも「考え方」や「行動」も褒めるようにすると、「なるほど、それはいい考えだね」って褒めることもできるし、「お、実際にやってみたんだね。いいね~♪」なんて言ってあげられますよね。
また、「褒める機会」が5つもあれば、何かしら褒めるきっかけはあるんですね。
よく「うちの子は褒めるところがありません」と言われる方も、見つかる可能性が高いのです。
そしてこの「褒める」目的というのは、子供が自分から「やってみよう♪」「頑張りたい♪」って前向きな行動ができるようになるための種まきみたいなもので、
「褒める」ができるようになると、子供たちが自信を持って行動することもできるようになるんですね。
でも、もしかしたら勘違いしている方もおられるかもしれないので、先に知っておいて欲しいのですが「褒めれば自信がつく」という考え方は間違いで、
「自信」はたくさんの経験の中で、たくさん失敗をして、その中から小さな「成功体験」を積み重ねていくことで
自分で「僕って、いいんじゃない?」「私って、なかなかやるじゃん!」「これもきっとできるよね♪」「ほらできた!」「やっぱり何度も練習すると上手になる!」のように考え方が変化していく。
その積み上げと、経過の考え方変化の中に「自信」があり、乗り越え方を覚えていくんですね。
それは、お母さんがすでに体験している「自転車」のように。
なんでも最初はうまくいくことよりも、失敗の方が多いけど、何度失敗しても繰り返し、チャレンジすることで、少しずつできるようになって、最後には「できる」自分になる・・・のです。
その経過で身につくものが「自信」なので、「自信をつけて欲しい」とお考えになるのなら、まずは「経験」を増やすこと。そしてそのための「褒める」なんですね。
また、もし「今まで叱りすぎていて、考えも行動もしてくれない」としたら・・・お母さんがそのシチュエーションを作る、ということもできます。
例えば、買い物に一緒に行って、重い荷物を持ってもらう。車まで運んでもらう。
その時に、「ありがとう。荷物を持ってくれてお母さん助かったよ」のようにお母さんが喜び褒めてあげることで、子供は
「お母さん、僕がこう言うことをすると喜んでくれるのか?」という「自分が褒めてもらえる機会」を経験することで、
お母さんの求めている方向がわかり、「じゃあ、こんなことをしたら褒めてくれるかな?お母さん喜んでくれるかな?」と自分で探して行動し始めるんですね。
もちろん、そこで、お母さんも気づいてあげて、その都度「◯◯、してくれているんだね。ありがとう」や「◯◯してくれたの?助かるな~」のように、
喜びを表すことで、子供はさらに「こんなことはどう?」「これも喜んでくれる?」といろいろ自らが行動して「喜んでもらいたい」ことをし始めてくれます。
そんなふうにお母さんからアクションを起こすことで、子供との関係は良くなるんですね。
他にも、次のステップの「包む」について、兄弟喧嘩が大事なことについて・・・
といろいろお話もしたのですが、とりあえずメインのことだけをご紹介させていただきます。
そして・・・今回、私も考えを新たにしたことがありました。
今回の講演会でわかったこと
それはママさんたちのAI普及率です。
私は「忙しいママだからこそAIを使うべき」とお話ししているように、ほとんどママさんがAIを『使っていない』と思っていました。
いえ、子育てをしている全体数からすると、まだまだAIを使っている人が少ないのが現状だとは思います。
ですが、0歳のお子さんがいらっしゃるような若いママさんたちは、半数ぐらいが子育てにもAIを使っておられました。
私にとっては、それは衝撃で、「さすが、デジタルネイティブの方々は、どんどん新しいテクノロジーを使うのだな!」と驚きました。
それでも、「こんな使い方があるんです」と、例えば義実家のことで相談したり、愚痴を聞いてもらったり、近くで子供連れで遊べる公園がありますか?と聞いたり・・・
こんな活用もできるんですよ。と実際にスマホを使ってご紹介した時には「え~。そんなふうに使うんだ」というリアクションもいただけました。
・・・・わ~、もうかなり長くなってしまった。
結果として10分間の休憩をいれて、ほぼ2時間喋りっぱなしで、先に作っていったシナリオ(カンニングペーパー)も全く見ずに、喉がかれました(笑)
でもこれ、動画を撮っていますので、また、ご覧いただけるようになりましたら、お知らせしますね♪
最後に、2026年のランチ会のお知らせをして、今日のメルマガは終わりとさせていただきます。(講演会のご依頼も遠慮なくどうぞ・お代はいただきません)
2026年
1月 沖縄県ランチ会
2月 静岡県ランチ会
3月 岡山県ランチ会
4月 長野県ランチ会
5月 富山県ランチ会
6月 茨城県ランチ会
ご連絡はパピーいしがみまで。
メール送信先:age18_jp@yahoo.co.jp
来週は、宮城ランチ会があります。こちらもまた、ご報告させていただきますね♪
https://www.age18.jp/ichiran.html
よろしかったらSNSもご覧ください♪
【Instagram】
https://www.instagram.com/papy_ishigami/
【YouTubeチャンネル】
「パピーいしがみ」チャンネル
【X(旧Twitter)】
https://twitter.com/papy_ishigami
【LINE公式アカウント】
https://lin.ee/CnDdGcd
【TikTok】
https://www.tiktok.com/@papy.ishigami
 【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。
【 パピーいしがみ 】人材育成の現場から、育児・子育てこそが、本人の一生のベースになると痛感し、吸収したノウハウやアイデアを自分の3人の子育てに応用。子供達が喜びと自信を持って成長していく中で、親としての充実感と予想をはるかに上回る結果に驚愕する。2003年あまりの少年犯罪の多さ、幼児虐待の事件に心を痛め、その子育て育児方法をインターネットで公開。熱烈なサイトのファンからの要望で、テキストを作成し通信講座として紹介。著書も好評で現在は会員さんから毎日届く悩みや相談に応えている。